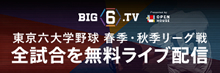バックナンバー
ホーム > バックナンバー > 倶楽部報2024年秋号 > 2024年秋号(三田倶楽部員奮闘記「野球部の4年間を振り返り、今思うこと」)
倶楽部報(2024年秋号)
三田倶楽部員奮闘記「野球部の4年間を振り返り、今思うこと」
横山 信之(昭和61年卒 開成高)
2024年09月13日
私が慶大野球部に入部したのは1982年、白い練習用のユニフォームに身を包み、初めて日吉のグラウンドに立った時のことは今でも鮮明に憶えている。1982年は故前田祐吉元監督(以下、前田監督)が2度目の監督に就任した年で、4年間を前田監督の指導の下で過ごした。最後のシーズンとなった1985年(昭和60年)秋にはチームは13年振りにリーグ戦優勝、その後の明治神宮大会も優勝して日本一になり、前田監督は試合出場が叶わなかった部員にも多くの景色を見せてくれた。現在、三田倶楽部理事を務める同期の蔭山実君から三田倶楽部報に寄稿するという倶楽部員として名誉ある機会をいただいたので、野球部で過ごした大学の4年間を振り返りつつ、思うところを綴りたい。
慶大野球部第一合宿所の正面玄関を入ったところには、『練習ハ不可能ヲ可能ニス』という文字が刻まれた版木が掲げられている。体育会の発展に力を尽くした故小泉信三元塾長(1933~47年塾長、以下小泉先生)が『スポーツがもたらす三つの宝』の一つとして挙げている言葉だ。前田監督が慶大に入学したのが1949年(昭和24年)なので、その選手時代は小泉先生の塾長時代とは重ならないが、前田監督の自著『野球と私』の中に小泉先生との邂逅に言及するくだりがあるのは興味深い。
時は1952年(昭和27年)。慶大野球部が小泉先生のすすめで、現在の東京都東村山市にあるハンセン病の療養所を訪問して紅白戦を行い、登板した前田祐吉投手が逆転ホームランを打たれて敗戦投手になった話である。『歓声を上げて初めて見たホームランを喜ぶ患者さんたちを見て胸が熱くなった。後にも先にも打たれて嬉しかったのはこの時だけであった。小泉先生のお世話でせめて一度でも野球によって不幸な境遇にいる人たちを慰めることができたのは貴重な思い出となった』と回顧している。ハンセン病に対する強い偏見と差別が支配的だった時代の出来事である。旧優生保護法が制定されたのが1948年、その隔離政策と強制不妊手術に違憲判決が出たのは実に2024年7月のことであり、当時の小泉先生と前田監督の心懐に思いを巡らせるに尊敬の念を覚える。
慶大野球部には、慶應のグレーのユニフォームを着て神宮でプレーすることを目指して全国から選手が集まる。名にし負う野球強豪校から来た選手もいれば、甲子園に出場していなくとも都道府県レベルで実績を残した選手も大勢いる。皆が試合に出場してチームに貢献することを夢見て野球部の門を叩くが、新入部員の多くは自分自身の試合出場を見通すことなどできない中で、日々練習のグラウンドに立つこととなる。ピッチャーだった私も、多くの点で(すべての点で、と言った方が正確か)、自分より優れた選手が数多存在する中にあって、自分に何ができて、何ができないのか、当然のことながら自分の力量についてはシビアに認識しなければならなかった。自分がやらなければならないことはチームの練習の一助となること。それはグラウンド整備であり、球拾いであり、バッディングピッチャーであり、ボール磨きなどであったが、各自がチームのためにそうした役割を果たすことは、言うなれば不文律だった。自分自身の練習はその上でのことになるが、それでも、昨日より今日、今日より明日と少しでも上手くなる様に努力を続けるしかない。大事なのは、単調な基礎練習を継続すること、小さな積み重ねを連続させること、練習で手を抜かないこと、やれることを毎日やって、少しでも調子を整えること(そうすることで大事なところで力を出せる可能性を少しでも高めること)、上を目指そうという強い意思を持ち続けること、(他方で)努力していればいつかは報われるという甘い考えは捨てること。そんなふうに考えていた。自分が心に刻んでいたのは『練習ハ不可能ヲ可能ニス』の言葉だ。前田監督の唱えるエンジョイベースボールが『各自が自分の役割を果たす』『チームの全員が常にベストを尽くす』『チームメイトへの気配り』『自ら工夫して、自発的に努力する』ことを核に据えていたので、試合出場のレベルに達していない(従いグラウンドでの実戦練習の機会も限られている)選手が、こうした心持ちで日吉のグラウンドで練習に臨み、日々野球と向き合っていたことは慶大野球部ではごく自然なことだったように思う。それは今も変わらないと確信するところだ。
私が1年から2年に学年が上がる前の1983年春に慶大野球部はアメリカに遠征した。前田監督がチームの意識改革と強化を意図して実現させたものだ。同期からは、遠藤靖、仲沢伸一、奈良暢泰、江端徳人、松井一夫が遠征メンバーに選ばれて参加した。この遠征でチームが学んだことは数多くあるが、最大の成果は投手陣が学んで持ち帰ったMoving Fastballだろう。当時は、ピッチャーの投げるストレートはきれいな回転で伸びがあり、手から糸を引くように真っすぐな球筋をたどってキャッチャーミットに収まるのが良いとされ、これを「生きたボール」と表現していた時代だ。アメリカで教えられたのは、こうした投球(ストレート)は球速が90㍄(約145㌔)を超えるものであれば、速球としてバッターを打ち取れるが、それに満たないレベルでは単に素直で打ちやすいだけ、従い球速が90マイルに満たない普通のピッチャーは球を動かすべし、ということだった。
具体的には、ボールを縫い目が縦に平行になるように自分に向け、そこを人差し指と中指の間を狭くしてやや深めに握り、真ん中低めを狙ってスリークオーター気味に腕を振って投げよ、という教えである。投球が低めにいけば、ボールはバッターの近くで必ず微妙に右か左に曲がりながら落ちる。この動き(=変化)で打者を打ち取る。バッターの手前でボールが生きているように動く。だからMoving Fastballだ。2学年先輩の永田博幸投手はアメリカ遠征直後の1983年のリーグ戦において、このMoving Fastballを武器に4年生の主戦投手として大活躍し、年間6勝を挙げた。Moving Fastballとチェンジアップを自由自在に操り、短い投球間隔で迷いなくストライクゾーンに勝負球をズバリと投げ込む。そのピッチングは、目を見張るような速球を持たない後輩のピッチャーたちの行くべき道を照らしてくれた。永田先輩のグローブの甲には『真向勝負』と書かれていたのを覚えている。全力投球とは一球に気持ちを入れること。Moving Fastballは今でいうところのツーシームであるが、これを前田監督がチームに伝授したのは実に40年前のことだ。加えて言うと、前田監督はOKボールとかサークルチェンジと呼ばれていたチェンジアップもアメリカ遠征でピッチャー陣に学ばせ、チームに持ち帰り、熱心に教えた。前田監督が常に合理的な理論と野球技術を求めて、時代の先をいっていた一つの例だろう。
秋のリーグ戦を前に4年生には万感こもごも到るものだ。ほとんどの選手は大学で野球を終えることになるので、文字通り最後のシーズンになる。思いを共有するのは同期のメンバーで、新入部員として日吉の野球部合宿所に集合した日から4年間、苦楽を共にしてきた仲間たちだ。1年生の時からレギュラーで活躍してきた選手、努力が実り上級生になって試合出場の機会を得た選手、試合出場が叶わぬ中で上級生となって(選手としての努力を続けながらも)チームに貢献できるところで最大限の役割を果たしてきた大多数の選手、誰もが気を入れてグラウンドに出て練習に臨む。チームの運営を支えてきたマネジャーもまた然りだ。
志を立てて入った野球部であっても、(4年間)日々連日、やる気を奮い立たせてグラウンドに出ることは必ずしも容易なことではない。行動するためには意志の力を働かせなければならないからだ。そして意志の力とは独りでに湧いてくるものではなく、培わなければならない。練習中に他の選手の真剣な眼差しと額を流れる汗を見て、神宮球場でチームの戦いを見て、そして、先輩後輩と切磋琢磨して競争する中で、同期のメンバーと深く交わる中で、寮生活の日常の中で、チームとして共通の目的に向かうことで生まれる一体感や高揚感を実感する中でと、あらゆる状況を通じて培うのだ。最後の秋のシーズンを迎える4年生は、そうした意欲に限界を感じることはもはやないだろう。あとはやりきるだけなのだ。
自分は、野球の能力、努力ともに及ばず、リーグ戦に出場してチームに貢献することは一度も叶わなかったが、日吉のグラウンドで何万球というボールを力の限り投げ抜いた4年間は充実したものだった。また、ピッチャーだった私は、前田監督の指導を受ける選手の傍らでその教えを聞いたり、時として直接教えを受けたりできたことは幸運で、本当に恵まれていた。感謝したい。
今の4年生が全員、野球部で最後までやり切ったという思いをもって卒業し、社会に出たらそれぞれのフィールドで活躍することを願って止まない。

1985年11月11日明治神宮大会決勝戦後の同期集合写真
(最前列3人の左端が筆者、最後列左から3人目が蔭山)

1985年平田寮の4年(左から筆者、喜多井健、秋山光)